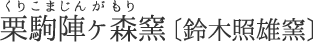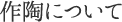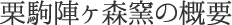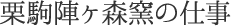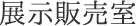私の作陶の姿勢は、
手仕事らしく自然に即した仕事のあり方を若年より求めたことにあります。
それ故に窯場のある姫松周辺より採取できる粘土と、
各種土石類を釉薬の主たる材料として使用しています。
焼成は薪の火による登り窯によるものです。
ロクロ成型は手廻しの「手ロクロ」と、足による「蹴ロクロ」を使用するものです。
これらの手法は農業においての有機、自然農法と通じるものがあり、
私の窯の製品は現在の多くの陶磁器商品とは趣を異としています。
色や形の均一性はありませんし、
かなり曲がったりしています。
また物理的機能性においても、
機械製品はもとよりガスや電気窯による焼成品には及ばない場合があります。
手触りの点でも、土を自主的に精製しすぎないようにしているため、
なめらかではありません。
地方の土はおおよそのところ、
製陶中心地の土よりも耐火性など多くの点で劣る場合がほとんどと申せます。
これらの弱点にもかかわらず、私の続けている手法は、
この地方の自然の恵みがこの上なく豊かに思える故であり、
本当に「焼物」といえるすばらしい多くのものはほとんど、
自然の美を内に宿していると見え、感動させられた故なのです。
私の作品はまだまだそんな領域から程遠いものですが、
皆様にせっせと使っていただけると日毎に色も深みを益し、
手触りも落ち着くと自負しております。
少々取柄のあるものとしても、
全て自然のなせる技と思われます。
お求め下さり器を育てて下さるのは、皆様と思っています。
限られた少量生産のため廉価とは申せませんが、
この現代において仕事を持続するのに精一杯の努めをいたします故、
今後とも御鞭撻のほど心よりお願い申し上げます。
鈴木照雄
栗駒陣ヶ森窯は、作陶に適した住環境を求め、2004年から2009年にかけて、栗原市一迫の栗駒姫松窯を現在地に移転・開窯したものです。
山間に位置するこの窯場は、茅葺の母屋を住空間とし、隣接するロクロ場、作業小屋、展示即売室、そして2基の薪窯からなっています。




仕事は原料の土の採取から始まります。
乾燥や水簸(すいひ)、土練などの様々な工程を経た後、ロクロによる成型を行ないます。
栗駒陣ヶ森窯では、蹴ロクロを主に、手ロクロも用いて成型しています。




栗駒陣ヶ森窯では、旧栗駒姫松窯から移築した連房式の登り窯と、竹割式の蛇窯(じゃがま・2012年完成)の2基を用いて焼成しています。
素焼は登り窯で行い、釉薬(うわぐすり)を掛けた後の本焼は、登り窯と蛇窯を併用しています。また、素焼を行なわずに釉薬を生掛けして焼成する場合もあります。




2012年開設の展示販売室では、常時栗駒陣ヶ森窯の製品を展示販売しています。